|
漆文化のはじまり
japanと呼ばれる漆器の歴史は、近年の考古学的調査によって約6800年前にさかのぼることが、明らかとなりました。その最古の漆塗り製品は、能登半島・田鶴浜町三引遺跡から出土した竪櫛です。16本の櫛歯(ムラサキシキブ材)に横木を渡して、植物繊維でより合わせ、頭部を半円形にしています。すでにベンガラ(赤色塗料)が含まれた漆を4層塗り重ねるなど高度な技術が駆使されています。縄文時代の櫛はシャーマン(呪術者)の頭部を飾る呪具で、多くは赤色漆塗りです。赤色は生命の色、再生の色であり、精製された漆に赤色顔料(ベンガラ・朱)を混ぜることによって、より光沢と深みをました麗しい赤色に変化します。またその強い粘着性は朽ちることなく物質の永遠性を保ちます。
このようにして漆は呪具を飾る必須の塗料となりました。かぶれる漆に恐れを抱きつつも、鮮やかな永遠の生命をたたえる漆は、カミが宿る樹木として信じられたのではないでしょうか。こうした森の民の思想は今日にいたるまで受け継がれています。本物の漆器にふれたとき、何者をも優しく包み、深い異次元の世界に引きこまれます。漆はまさにいやしの塗料なのです。
|

田鶴浜町三引遺跡出土の縄文竪櫛 |
|
古代・中世の漆器
平安時代の説話文学集『今昔物語』に、あらゆる願いがかなえられるという「通天の犀角帯」入りの漆桶が、輪島の海岸に漂着したという話が収められています。輪島と漆を結びつける文学上の最古の記録ですが、潮が運ぶ能登の文化的位置を示しています。同時代の輪島で漆器が作られていたことは、石川県輪島漆芸美術館前の釜屋谷B遺跡から、漆盤(大皿)と漆パレットが出土したことからも、裏付けられています。
漆器の生産はいくつかの分業を総合した高度な技術で、古代においては律令国家や有力寺院などに掌握されていました。平安時代も後期になると国家権力は衰え、漆工技術者たちは保護を求めて地方の富豪層のもとに身を寄せたり、山々を漂泊して簡素な漆器作りを行う木地師たちが出現しました。こうして平安時代末期から中世にかけて爆発的に漆器の普及が始まり、飯椀・汁椀・采椀の組み合わせ(組椀)が食膳の主流となりました。富豪層の居館跡と考えられる山岸遺跡からは多量の漆器が発見され、輪島においてもかなり普及していたことが知られます。
|

漆盤 |
|
輪島塗のおこり・産地の形成
中世後期の輪島は大屋荘の中心であり、日本海側を代表する「親の湊」をひかえた中継港湾都市として栄えました。
富山湾側の中核集落・穴水町西川島遺跡群御館遺跡から出土した線刻椀(室町前期)には輪島沈金と同じ技法がみられるとともに、顕微鏡分析から珪藻土の下地が確認されました。つまり今日の輪島塗の特徴を備えた最古の漆器ということになります。
 輪島塗と他産地とを識別する最大の特色は、下地に地の粉(珪藻土)が用いられていることです。これを焼成粉末にして下地塗りに用いますが、微細な孔を持つ珪藻殻の粒子に漆がよくしみこみ、化学的にも安定した吸収増量材になることと、断熱性に優れていることが重要な特色です。つまり漆とガラス質の微化石・鉱物による固く堅牢な塗膜によって柔らかいケヤキの木地が包まれ、くるい(変形)がなく熱に強い漆器の基礎ができあがるのです。輪島塗が堅牢無比といわれる理由はここにあります。 輪島塗と他産地とを識別する最大の特色は、下地に地の粉(珪藻土)が用いられていることです。これを焼成粉末にして下地塗りに用いますが、微細な孔を持つ珪藻殻の粒子に漆がよくしみこみ、化学的にも安定した吸収増量材になることと、断熱性に優れていることが重要な特色です。つまり漆とガラス質の微化石・鉱物による固く堅牢な塗膜によって柔らかいケヤキの木地が包まれ、くるい(変形)がなく熱に強い漆器の基礎ができあがるのです。輪島塗が堅牢無比といわれる理由はここにあります。
従来このような下地技法は江戸時代の寛文年間に生まれたとの伝承から、輪島塗の起源をここに求める考えが定説化していました。しかし室町時代にさかのぼる考古資料が発見されたことや輪島市内の重蔵神社に残る文明8年(1476)の棟札に塗師たちの名前がみえること、明和5年(1768)に修理された同社奥の院の朱塗扉は、大永4年(1524)造替時のものといわれていることなどを総合すると、室町時代には国人領主・温井氏の保護のもとに漆器生産が行われ、小規模な商圏が形成されていたと考えられるようになりました。
 朱塗扉 朱塗扉
|

線刻漆椀
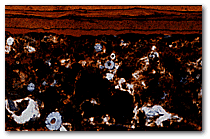
線刻漆椀・塗膜の顕微鏡写真

地の粉の焼成
機械化以前は野焼きにしていた
|
|
輪島塗の発展 江戸時代
17世紀以降、輪島近辺に産する漆、アテ(ヒバ)、ケヤキ、輪島地の粉(珪藻土)などの豊富な材料を用いて分業的生産による堅牢な漆器作りを行い、港湾機能を生かして広域的な市場を形成して発展したものが近世輪島塗です。
すでに江戸時代前期の寛文年間(1661〜1672)には敦賀をへて、京・大阪に販路を広げていました。正徳3年(1713)の塗師数は25名ほど、天明7年(1787)には河井町50人、鳳至町12人、天保14年(1843)には鳳至町だけで塗師28軒、塗師職人79軒となりました。生産組織も塗師、椀・曲物・指物木地、蒔絵、沈金の六職となり、分業化がいっそう進展しました。こうした状況を反映して18〜19世紀にはご膳や椀・櫃が、西は山口県(赤間ヶ関)から、北は北海道にまで運ばれており、天保12年(1841)にはエトロフ島からも注文が入るほどでした。このため漆が不足し新潟方面から調達していました。
輪島塗が大きく発展した要因をいくつかあげてみましょう。
1.漆や地の粉など豊富な素材に恵まれ、気候が漆器制作に適していました。
2.17世紀後半(寛文年間)には今日と同じ堅牢な技術が確立し、これが評判を呼びました。
3.徹底した品質管理を行いました。天明年間(1781〜1788)には、笠屋佐次右衛門ら10名が発起人となり「大黒講」を組織し、塗物の製造工程を定め、価格、販売区域の協定、違反者への罰則などを決めました。これが信用を呼び「場所」とよばれる販路拡大につながりました。
4.六職とよばれる生産の分業化がはかられ、量産体制が整いました。また輪島の周辺には木地師の集落がいくつもありましたが、安価な陶磁器の普及によって彼らの生活がなりたたなくなると、輪島塗の木地師となって生産を支えました。
5.「椀講」「家具頼母子」とよばれる販売方法によって京・大阪方面での販路が拡大しました。これは行商先で10人の顧客を募り一講を組織するとすれば、商品の価格の1/10を各人10回出資することと定め、商品は抽選順番によって10年間にわたり毎年納品される方法です。顧客にとっては求め易く、塗師にとっても安定した需要が見込める合理的なものです。もちろん販売は塗師屋が直接購入者に納める行商制であり、対話を通しての信用販売でした。
6.日本海側を代表する良好な港をひかえ、廻船で各地に大量に製品を運ぶことができました。
|

輪島港

江戸時代のロクロ
|
輪島塗の発展 明治・大正時代
明治維新によって大名・武士、公家などの需要を失った京都、江戸、尾張、加賀などの漆器産地は大きな打撃を受けました。しかし飯田善七はじめ藩のお抱え職人が輪島に移住したこともあって、富裕な農家や商家を主な顧客とし、独自の生産・販売形態をもっていた輪島塗は、かえって生産を発展させることになりました。
明治後期から大正時代にかけては、三代沈佐・橋本雪洲や黒川碩舟、舟掛宗四郎、舟掛貞二らの沈金の名工が輩出し片切彫や沈金象嵌などの新たな技術も開発されました。また伝統的な家具(膳椀セット)の製産に加えて、料亭や旅館で使用される業務用の需要を開拓し、製品の種類に変化が生まれています。
明治18年(1885)には、輪島地の粉(珪藻土)の管理、漆樹の植栽、職人の技術向上を目指して、輪島漆器同業者組合が結成されました。明治36年(1903)の河井町の塗師屋は157軒、鳳至町の塗師屋は61軒。明治43年(1910)の輪島漆器同業者組合加入の漆器業者は255軒を数えるまでになりました。
輪島塗の発展 昭和〜現代
昭和2年(1927)には帝展に工芸部門が新設されました。輪島では蒔絵師竹園自耕や、沈金の前大峰などが帝展を舞台に漆芸作家として活躍を始めます。昭和5年(1930)には、前大峰が帝展特選を受賞。戦後は毎年のように中央展での受賞を重ねる作家たちが多数輩出しています。
昭和29年(1954)に工芸展が日展と伝統工芸展に分かれると、今日まで日展では張間麻佐緒、榎木盛、三谷吾一、井波唯志、角野岩次らが指導的な役割を担い、大きく工芸界に貢献しました。一方、伝統工芸展では昭和30年(1955)に前大峰が、(漢字なし-髪の下半分が休っつー字-)漆の塩多慶四郎が平成7年(1995)に、沈金の前史雄が平成11年(1999)にそれぞれ国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の指定を受けました。他に漆や木などの素材美を生かした作品を手がける角偉三郎らがいます。
昭和50年(1975)には輪島塗が伝統的工芸品に、昭和52年(1977)には重要無形文化財に、昭和57年(1982)には輪島塗の制作用具など3804点が重要有形文化財に指定されました(輪島漆器資料館で常設展示中)。平成3年(1991)には、全国初の漆芸専門美術館として石川県輪島漆芸美術館が開館しました。常設の輪島塗、現代漆芸作品やアジアの漆芸品の他、おりおりの企画展などによって漆工芸の名品に接することができるようになりました。
|
