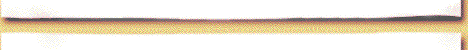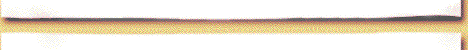|
10.一辺地付(いっぺんじづけ) 一辺地漆を面ごと何回かに分けてへらを使って全体に塗ります。お椀の縁など特に丈夫にしたい所はひ皮へらをつかって地縁引きをします。
一辺地漆は珪藻土を蒸し焼きにし砕いてふるい分けた地の粉(一辺地粉)と生漆と米のりを混ぜたものです。二辺地、三辺地と進むごとに米のりの割合を少なくし地の粉の粒子も細かくなっていきます。
11.一辺地研ぎ かたい砥石を使い全体を空研ぎする。
12.二辺地付(にひんじづけ) 二辺地漆を一辺地同様に全体に塗る。
二辺地粉+生漆+米のり+砥の粉
13.二辺地研ぎ かたい砥石を使い全体を空研ぎする。
14.三辺地付(さんぺんじづけ) 三辺地漆を二辺地同様に全体に塗る。
三辺地粉+生漆+米のり+砥の粉
15.三辺地研ぎ かたい砥石を使い全体を空研ぎする。
16.めすり 砥の粉と生漆を混ぜたさび漆を薄く塗り肌を細かくする。
17.地研ぎ 下地が仕上がってから全体を砥石でていねいに水研ぎする。
|